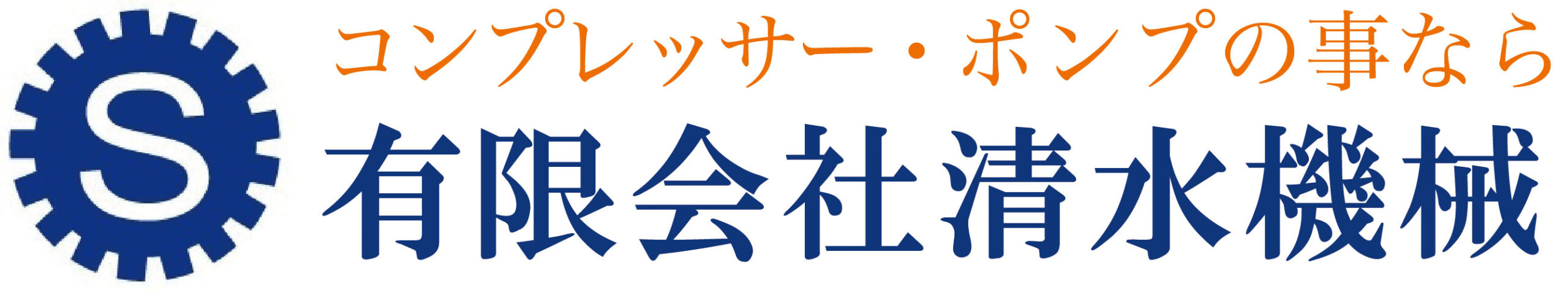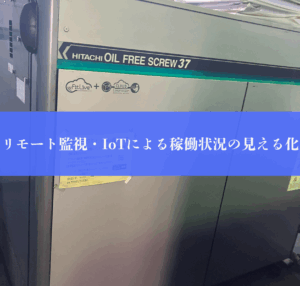コンプレッサーの騒音対策!工場の防音対策で作業環境を改善
「コンプレッサーの音がうるさい…」「従業員や近隣から苦情が来てしまった…」
そんな現場の悩みを解決するには、的確な騒音対策と防音対策が必要です。
この記事では、コンプレッサーの騒音の原因から対策方法、防音材の選び方や施工のポイントまで、
機械設備の専門家がわかりやすく解説します。
目次
コンプレッサーの騒音はなぜ発生する?
コンプレッサーの運転中には、次のような要因から騒音が発生します。
| 発生源 | 内容 |
| 吐出音 | 圧縮された空気が急激に解放される音(特にピストン式) |
| モーター音 | 電動モーターの回転音、ベルトやギアによる伝達音 |
| 振動音 | コンプレッサー本体の振動が床や架台に伝わる音 |
| 吸気音 | 外気を吸い込む際の吸引音 |
特にピストン式やレシプロ式のコンプレッサーでは、機械構造上、連続的で周期的な打撃音が大きくなりがちです。
※レシプロ式コンプレッサーの構造に関する記事はこちら
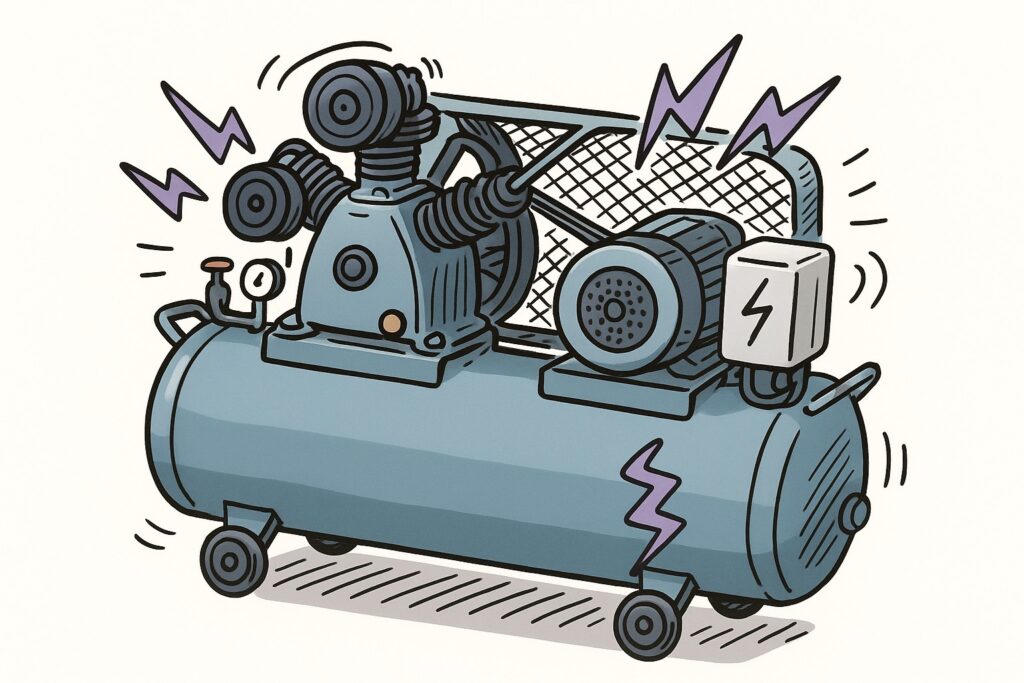
騒音対策が必要な理由
騒音による注意点と事例
- 労働環境の改善(騒音障害・耳鳴り・集中力低下の予防)
- 近隣住民からの苦情防止(工場外に音が漏れるケースも)
- 作業者の安全確保(音声指示が聞こえにくいと危険)
- 法令対応(労働安全衛生法・騒音規制法など)
コンプレッサーの主な騒音対策方法
防振ゴム・防振パッドを使う
床面に伝わる振動音を吸収する素材を使うことで、二次的な騒音(反響音)を抑制します。
レシプロ式コンプレッサー防振ゴムを設置しているお客様をよく見かけます。
吸排気経路の見直し
吸気音や吐出音の発生源となる配管にサイレンサー(消音器)を設置し、音の拡散を防ぎます。
防音サイレンサーは後付け可能で効果が大きいです。
設置場所の工夫(屋外設置・隔離)
建屋内ではなく屋外や専用防音室に設置することで、作業エリア内の騒音を大幅に軽減できます。
騒音源から作業者までの距離を取るだけでも効果があります。
静音タイプのコンプレッサーへ更新
思い切って静音型・オイルフリー型・スクリュー式コンプレッサーに更新することで、根本的な解決も可能です。
中でも、スクロール型のコンプレッサーは静音性がかなり高いです。
騒音レベルの目安と許容基準(dB)
| 騒音レベル(dB) | 状況 | 対策必要度 |
| 70〜80dB | 大声で会話が必要なレベル | 中〜高 |
| 80〜90dB | 長時間の作業で難聴リスクあり | 高 |
| 90dB超 | 短時間でも防音対策が必須 | 非常に高い |
※ 労働安全衛生法では、85dB以上の環境での作業に耳栓や保護具の着用が義務付けられています。
防音対策の施工ポイントと注意点
防音対策の施工ポイントと注意点
- 換気・冷却性能を損なわないよう、防音ボックスには通気設計や排熱口の確保が必要
- 遮音と吸音のバランスを考慮(反射を減らしながらも外部漏れを防ぐ)
- 防音材は耐久性や難燃性にも注意
- 防音室を作る際は、メンテナンス用の開口部(点検扉)を設けること
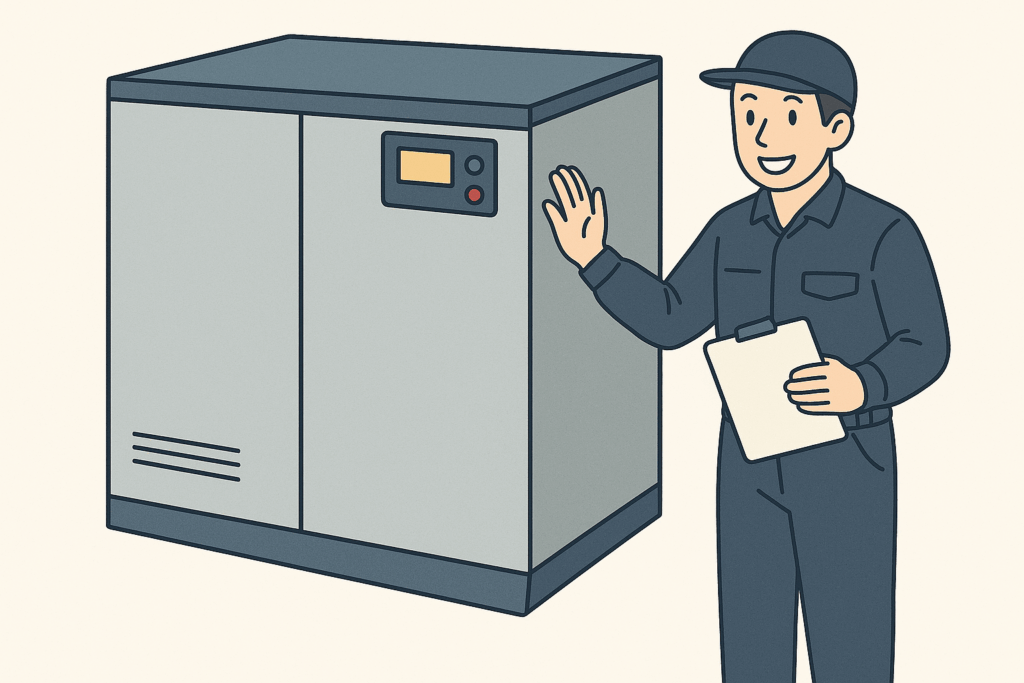
まとめ:騒音対策は「設備の快適性と安全性」を守る第一歩
コンプレッサーの騒音は放置すれば、労働環境の悪化や企業イメージの低下につながる問題です。
対策を講じることで、作業者のストレス軽減や近隣対応のリスク低減にもつながります。
小さな対策でも、積み重ねることで大きな効果が生まれます。
まずは現状の音源を特定し、「できる対策から始める」ことが騒音改善の第一歩です。
音源の特定が困難、従業員や近隣から苦情が出たが対応する時間がなかなか取れない等、
困りごとがありましたら是非お問い合わせください。